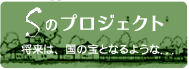日本のすがた・かたち
「お母ちゃんはお前を信じてるからね。」
郷里の網代駅から横浜行きの電車に乗る朝、切符を渡した母は、私の眼を見てこの一言をいいました。
52年前、小さな行李とギターを持ち、不安と希望が交じる別れの早朝でした。
駅のホームには満開の桜が咲いていました。
十八になるまで家の前の海と母と離れたことはなく、前の年に父を亡くしたこともあり、この朝は、母と今生の別れになると思い辛いものでした。
車窓から朝陽に煌く相模の海を見ながら、これで独りぼっちになったと思い、涙が溢れたのを覚えています。
あれから横浜で暮らした四年間は、刺激的ながら荒んだ生活でした。
道をはずれることや、お巡りさんにご苦労かけ、今にして思うと赤面の至りといえる日々を過ごしました。
その折々に聴こえてきたのが母のこの「信じているからね」の金言でした。
その度に、父母や兄弟に抱きしめられながら育てられてきたと思えたものでした。
人は物心付く頃から親や周りから愛情を注がれて育つと、生きて行く自信というか、「自分はこの世に生きていて良いのだ」、という確信のような安堵感が持てるようです。
例え独りになっても、この愛情を注がれた子供の頃の実感は終生、生存への支えとなるように思います。天涯孤独に育った子でも、周りから傾注された愛情はこの世に暮らす者にとっての通行手形のようなものです。
人は生まれ育ち、家族と別れ、独り立ちをし、出会いと別れを繰り返し、やがて生を終えます。万人に差別なく、誰も文句なく、営み、繰り返す生々流転の様です。
それから先は人それぞれで、人生は楽しいと思える者はそう思えるし、苦しみと思える者は苦しい。その思い方にばらつきがでることは誰も阻止できません。
釈尊は人間生きることの一切は「苦」と看破し、その苦楽の境を「自分の心が決める」といっています。
幸不幸、苦楽の境を決める心は何を頼りとするのか。その頼りは、子供の頃に注がれた無償の愛のようです。
四月の初めになり、爛漫と咲く桜を見ると郷里を離れた折の情景を思い出します。
そして幾つになっても母の一言は響いています。
桜の樹の下で、子供たちの声が走り回っています。
写真: 京都 醍醐寺の桜