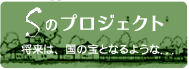日本のすがた・かたち
ねがはくは花のしたにて春死なん そのきさらぎの望月の頃
西行法師は、花や月など美しいものの象徴と、覚りを得たお釈迦様の入滅日にあこがれ、これを詠んだといいます。
春になると、決まって桜を観に行くのが習慣になっていて、この春も花見に出かけました。
私の場合、満開の桜の下にて酒を酌み交わすといった粋なものではなく、何となく眺め歩いてくる、というもので、どうも、桜を観るというよりも、桜のもとで、そこはとなく漂う寂しさを連れて歩いているようなものです。
満開の桜がハラハラと散り始めると、私はなぜか高揚します。
わずかな時間を生きて、そしてはかなく散る。これがいいのかもしれません。
京都を始め桜の名所で行けるところは回っていますが、花もさることながら、私は桜の大木にも気を惹かれています。
桜の木はどちらかというと異様な樹姿をしていて、老木は一様にオドロオドロしています。
ケヤキやクスのように、すっきりしていることが少なく、黒々と魔の手のように伸びたものが多くみられます。
それに淡いピンク色の可憐な花が咲く、それも固まりとなって、あたかも死霊が花のもとに潜むかのような様相です。
桜をなぜ日本人は好むのか、桜を観るとなぜ詩歌を詠みたくなるのか、なぜ唄うのか。
もしかすると、寂しいからかもしれません。
この世に生きていること、そのものが寂しいのかもしれません。
木を伐りながら仕事をしている私は、桜の木も好んで使います。
この木の中に、花びらが潜んでいたんだと思いながら……。
”散る桜ならぬ恋にもまたしきり” (『建築相聞歌』)
(写真 京都醍醐寺の桜)